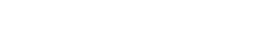近年日本ではオンラインカジノの取り締まりに関する議論が盛んに行われており、政府はこれらのオンラインカジノサイトへのブロッキングを検討していると述べました。一方、国際的に見てみると、多くに国がオンラインカジノやブックメーカーなどのライセンス制度を導入し、合法化すると同時に規制をかけ、経済的利益を得る方向に進んでいます。
その流れの中で、シューンゲル氏はグレーマーケットの新しい取り締まり方が出てきていると述べています。本ページでは、Sigmaの以下の記事を参考に今後の日本でのオンラインカジノのあり方について考えていきます。
オンラインカジノのライセンスを導入する国が増えている
マナビア・リミテッドのeGamingライセンス専門家であるフランク・シューンゲル氏は、iGaming業界におけるグレー市場からの脱却が進んでいると指摘しています。
ASEANゲーミングサミットでの講演で、「近年、多くの国が独自のライセンス制度を導入しています」とシューンゲル氏は述べ、その背景には政府が規制を導入することで得られる経済的利益に気付き始めたことがあると分析しました。一方、規制に苦戦している国もあることから、フィリピンのバランスの取れた規制手法を高く評価し、「他のアジア諸国、さらには世界中の国々にとって、模範となる例だ」と述べました。
不適切な規制のリスクも
シューンゲル氏は、不適切な規制がオペレーターやプレイヤーを未規制市場に追いやるリスクがあると警鐘も鳴らしました。例えば、コロンビアが提案した入金額に対する18%の付加価値税(VAT)は、消費者をグレー市場のオペレーターへと誘導する可能性があると指摘しています。
「ほとんどのオペレーターはルールを守ることに前向きです」とシューンゲル氏は語る。「適正なビジネスが成り立つのであれば、誰も影に隠れたいとは思いません。」 さらに、政府が適切なバランスを取る必要があると強調し、「利益が出せなければ、規制を守ることもできない」と述べました。
規制が厳しすぎると、ユーザーへの還元もできいなくなる
ライセンスを導入して厳しい規制を取り入れ、税収入を得ることには賛成なのですが、やはり厳しすぎる規制は逆効果のようですね。規制が厳しすぎるとオンラインカジノ側もビジネスにならず、ユーザーにも還元ができず、結局規制が緩いグレーマーケットにユーザーも移動してしまうという悪循環が生まれているようです。
もし日本がライセンス制度を取り入れることになったら、参考にしたい点ですね。
ブロッキングの効果は無し?取締り戦略の変化
シューンゲル氏は規制当局の取締手法の変化にも言及しました。日本政府は昨今の調査を経て、ブロッキングを検討していると述べていましたが、実はこのブロッキングは効果がないことが既に証明されています。
「昔はURLをブロックするだけでしたが、それは完全に無意味でした」とシューンゲル氏は述べ、韓国やオーストラリアの規制当局がウェブサイトをブロックしても新しいコピーサイトがすぐに登場していたことについて触れました。
それを受けて、近年ではサプライヤーへの圧力を強める戦略へとシフトしているようです。現在、規制当局は未認可のオペレーターと取引するサプライヤーに圧力をかけることで、市場の健全化を図っており、「合法市場を失いたくなければ、サプライヤーも慎重にならざるを得ません」とシューンゲル氏は指摘した。
日本も決済代行者などの規制は行っているものの、課題も。
サプライヤーを規制する点では、日本でも決済代行業者の規制を始めようとしています。しかし、決済代行業者の中には電子送金と呼ばれるものが存在し、ペイズやJetonなどは海外のサービスです。そのためこれらに日本の警察がどのように動く事ができるのかはわかりません。さらには海外の仮想通貨取引所などを利用している場合なども、完全な規制などは可能なのでしょうか。
他の国の様子を見ていると、規制を行っても何かしらの方法でユーザーはこれらのサイトにたどり着く事ができてしまうということは、既に証明されているようです。
今後の日本の対策に注目
今、日本でのオンラインカジノを取り巻く状況は日々変わってきています。政府は規制強化の方向に向かっているようですが、他の国の状況などを見てみると完全に排除することは難しい事が分かります。
統合型カジノリゾートのIRも経済的な理由から合法化することになったように、日本もライセンスの導入などの方向に舵を切るのも一つの手だと、私は考えます。既にライセンスを導入した国はたくさんあるため、フィリピンの規制の仕方などを参考に日本でも同様な措置を行うことは容易でしょう。